学部・大学院の紹介
栄養学科
管理栄養士に求められる「実践力」と「人間性」を育みます。

管理栄養士の役割は、人が生きるために必要不可欠な「食べる」ことを通して健康の保持・増進をサポートすることです。
一人ひとりの年齢や生活状態を観察し、科学的根拠に基づいて総合的に判断する力が求められます。
そのために、厚生労働省の規定を上回って履修できる臨地実習を設け、実践力の強化に大きな力を注いでいるのが天使大学の特徴です。
また、今日の管理栄養士の活躍の場は多岐にわたります。
患者さんに合わせた食事指導、成長期の子どもたちに必要な栄養を考えた献立作り、さらには福祉や地域行政など、さまざまな場面で「人」と向き合う専門職業人として、その人の思いや不安に寄り添う気持ちが大切です。
本学ではキリスト教的人間観に基づき、豊かな人間性とコミュニケーション能力を育むための学びに重点を置いています。
一人ひとりの年齢や生活状態を観察し、科学的根拠に基づいて総合的に判断する力が求められます。
そのために、厚生労働省の規定を上回って履修できる臨地実習を設け、実践力の強化に大きな力を注いでいるのが天使大学の特徴です。
また、今日の管理栄養士の活躍の場は多岐にわたります。
患者さんに合わせた食事指導、成長期の子どもたちに必要な栄養を考えた献立作り、さらには福祉や地域行政など、さまざまな場面で「人」と向き合う専門職業人として、その人の思いや不安に寄り添う気持ちが大切です。
本学ではキリスト教的人間観に基づき、豊かな人間性とコミュニケーション能力を育むための学びに重点を置いています。
| 入学定員 | 90名 |
|---|---|
| 修業年限 | 4年 |
| 卒業に要する単位 | 127単位(教養教育科目を含む) |
| 学位 | 学士(栄養学) |
| 卒業時の取得資格 | 詳しくはこちら |

4つの特長
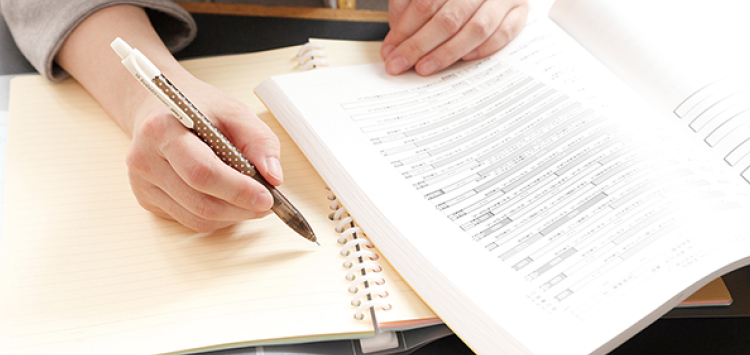
国家試験と就職に強い
- 全国平均を上回る国家試験合格率を支えるサポート
- 毎年100%の就職率を支える就職サポート
- 北海道内各地の医療・福祉施設や給食委託会社、企業と幅広い分野への就職
- 札幌市の栄養職員採用と教員採用試験(栄養教諭)合格の高い実績

管理栄養士と栄養教諭を養成するカリキュラム
- 臨床の場に強く、人の心に寄り添える管理栄養士養成のためのカリキュラム
- 子どもたちの食育を担う栄養教諭の養成カリキュラムも履修可能
- 天使大学大学院への進学でさらに高度な栄養学の学修も

“臨床の天使”質の高い臨地実習
- 国の基準(4週間)を大幅に超える最大9週間の臨地実習体験を実現
- 臨地実習施設は病院、福祉施設、小学校、保育所、保健所など多彩で豊富
- 病院での実習は3年次(必修)と4年次(選択)の2度にわたる履修が可能

学生参加による社会連携事業
- 札幌市東区との連携事業での食事指導・健康教育など
- 大学祭で地域の方々を対象に健康チェック
実習・演習の紹介
1年次
栄養学を科学的に学習するための基礎を身につける
食品科学実験Ⅰ
カリキュラムで登場する最初の実験科目で、化学系実験に関する基礎知識や基本操作、レポ-トの作成法を学ぶとともに、食品に含まれる成分について定量分析(どんな成分がどれくらい含まれているか)、定性分析(いろいろな成分の性質を確認すること)を行います。タンパク質・糖質・無機質など食品成分の理解と実験における数量的な扱い方を学び、さらに食品成分表に対する理解も深めていきます。
この科目で学ぶことは、栄養学を科学的に学習していく基礎となりますので、1年次にしっかり基本を身につけます。

2年次
一連の給食運営を学ぶ
給食経営管理論実習Ⅰ
学校や病院、保育園、高齢者施設などで食事を提供するための基本となる給食運営のあり方を学ぶ実習です。学内の学生や教職員を対象とした給食を作り、実際の昼食として提供しますが、それはまず栄養量を決めるところから始まります。献立を立て、食器や盛り付け方、サービスの方法などを考え、具体的な調理計画を立て、それらを限られた時間の中で実施します。
また、給食をおいしく衛生的に提供する方法を検討したり、給食を通して行う栄養教育を理解するために、ポスターやリーフレットの作成方法なども学びます。


作成された献立は、「天使の給食」というホームページで一般公開されています。
原稿の整理や写真の撮影など、インターネットを利用する情報提供に必要なことも、実習の中で学んでいます。
原稿の整理や写真の撮影など、インターネットを利用する情報提供に必要なことも、実習の中で学んでいます。
3年次
健康・栄養指導の実際を学ぶ
栄養教育論実習
すべての人々が健康で長生きするにはどのような栄養素が必要で、そのためにどんな食生活をしたらよいかを指導する技法を実習します。身体の計測や食生活・栄養摂取調査を行い、個人・地域・集団などそれぞれの対象者に対応した指導のプログラムを作成します。指導の成果を上げるために、既存のフードモデルなどを使いますが、状況や目的に応じて各自のアイデアを凝らした教育媒体を作成します。
小学校や保健所など、学外実習で栄養指導を体験した後は、指導内容全般に対する分析や評価を行い、その結果を次の計画に活用する方法も学びます。

患者データに基づいた栄養ケアプロセスを学ぶ
臨床栄養学実習II
食事をとることができない症例や食事に制限のある症例について、情報を整理し栄養アセスメントを行い、栄養ケアプランを作成します。栄養プラン作成にあたっては、その根拠をきちんと説明できるか、対象者の生活の質(QOL:qualityoflife)を考慮しているかをグループワークで議論します。さらに、作成した栄養ケアプランに基づく栄養・食事計画を作成し、実際に調製・調理と評価を行います。

4年次
臨床現場を希望する学生のために
臨床栄養学実習Ⅴ(学外実習)
臨床栄養領域では、3年次の「臨床栄養学実習Ⅲ」で全員が医療施設において2週間の臨地実習を行います。その後、より深く臨床栄養分野を学びたい学生は、さらに3週間の病院での「臨床栄養学実習Ⅴ」を選択することができます。この実習では、いろいろな事例を通して、ヘルスプロフェッショナルの一員としての管理栄養士の役割や、他職種との連携について学びます。また、臨床栄養管理のシステムや対象者一人ひとりに適した栄養補給、栄養教育などの方法を実践的に学び、総合的なマネジメントの考え方を理解します。

学習を体系化し、実践力を高める
卒業研究
専門領域における実践・応用力を高めるため、個人または数名のグループで研究に取り組みます。研究は、これまでの学習を体系化できるよう、学生自身で興味のあるテーマを選択して進めていきます。最後に研究報告をまとめて論文を作成し、集大成として研究発表を行います。
演習テーマ例(2019年度)
- 知的障害者の栄養管理における現状と課題
- ケータリング事業における商品開発~牛肉料理の調理法~
- 北海道の食文化~漬け物について~
- 自然災害時のたんぱく質確保に関する研究~低栄養を予防するために~
- 市販のプロテインバーのリン含有量
- 食物繊維の種類と血糖値上昇抑制効果の関係
- えん下困難者向けパン粥ゲルの物性に関する研究

